日本でマイノリティ(社会的少数者)と呼ばれる人々は様々いる。何をマイノリティとするか、そもそもマイノリティと考えることの是非はあるが、人種、病気、障害、家庭環境などが多種多様な人々が登場し、その人なりのそれぞれの日常が描かれていることも、本作の特徴である。
キャラクターとエピソード
ここでは、その中でも魅力的なキャラクターや、特徴的なエピソードを紹介する。
早坂 兵衛(はやさか・ひょうえ)
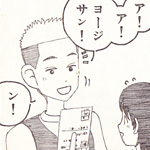 耳が聞こえない青年。耳が不自由な人は、発声に障害がなくても、自分の声が聞こえないため、話すことに恐怖を感じる人も多いと聞いたことがある。だが彼は、手話を使ったり、筆談したりしているシーンも描かれてはいるが、主に読唇で相手の意図を読み取り、自分の意志は発声して伝える。いつもニコニコとし、周りには常に人がいて、誰からも愛されるキャラクターだが、彼の過去は描かれておらず、そんな人物になった背景は知る由もない。年齢も明らかにされていないが、働いているからおそらく桂と同じぐらいか少し上であろう。
耳が聞こえない青年。耳が不自由な人は、発声に障害がなくても、自分の声が聞こえないため、話すことに恐怖を感じる人も多いと聞いたことがある。だが彼は、手話を使ったり、筆談したりしているシーンも描かれてはいるが、主に読唇で相手の意図を読み取り、自分の意志は発声して伝える。いつもニコニコとし、周りには常に人がいて、誰からも愛されるキャラクターだが、彼の過去は描かれておらず、そんな人物になった背景は知る由もない。年齢も明らかにされていないが、働いているからおそらく桂と同じぐらいか少し上であろう。
崔 月姫(チェ・ウォルヒ)
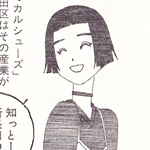 桂の学部の先輩、在日韓国人三世の崔月姫は、日本名の「千田姫子」ではなく本名の韓国名を名乗る。まぁ「千田姫子」はちょっとダサイかも・・・とは思うけど(いらっしゃたらスミマセン)、そういう問題じゃないよな。
桂の学部の先輩、在日韓国人三世の崔月姫は、日本名の「千田姫子」ではなく本名の韓国名を名乗る。まぁ「千田姫子」はちょっとダサイかも・・・とは思うけど(いらっしゃたらスミマセン)、そういう問題じゃないよな。
彼女曰く在日三世は、祖国を大事にして韓国語バリバリの人もいるし、帰化して名前も変えて日本人になりきっている人もいるという。そんな中で彼女自身は、もしかすると中途半端さを感じることもあるのかもしれないが、それでも「『月姫』のほうが『姫子』よっかかわいーやん?発音も好きやし」という理由で本名を名乗るという選択をしている彼女は、とても強く軽やかに見える。差別による嫌がらせを受けた経験も描かれているが、だからといって周りに合わせるわけでもなく、状況を恨んで殻に閉じこもるわけでもない。彼女自身のバランスで、自分の祖先のルーツである国と、自分が生まれ育った国とを受け入れている、しなやかで非常に魅力的な人物である。
小西さん
 日和の行きつけであるカフェ「キネマ」のマスターで、同性愛者。若いころはブラジルにいて、「フリオ」と言う名の恋人がいた(むろん、男性である)。しかし周りからは許されず、半身をもがれる思いをしながら帰国。「自分の命が残りわずかやってわかったら そしたら会いに行くと思う それでやっと会いに行けると思う 人生の最後に 何らかの価値を見いだす為に」と語っていた。店の改装をきっかけに、渡伯(身体に異常があったわけではない)。かつての恋人に会えたかどうかも、帰国した様子も描かれてはいない。
日和の行きつけであるカフェ「キネマ」のマスターで、同性愛者。若いころはブラジルにいて、「フリオ」と言う名の恋人がいた(むろん、男性である)。しかし周りからは許されず、半身をもがれる思いをしながら帰国。「自分の命が残りわずかやってわかったら そしたら会いに行くと思う それでやっと会いに行けると思う 人生の最後に 何らかの価値を見いだす為に」と語っていた。店の改装をきっかけに、渡伯(身体に異常があったわけではない)。かつての恋人に会えたかどうかも、帰国した様子も描かれてはいない。
近年は少しずつ理解されるようになったとは言え、性的マイノリティは生きづらい世の中であろう。例えば同性同士の婚姻が認められるようになるのは時間の問題のような気もするが、カミングアウトできる人ばかりではない。法があることと、世の中から受け入れられるということはイコールではない。LGBTは流行でもファッションでもなく、当事者たちの紛れもない日常である、ということを、忘れてはならないと思う。
余談だが、私はこのマスターの喋り言葉がとても好きだ。都会的で洗練された関西弁であると思う。
高橋愛
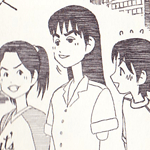 自称・隻腕の美女。桂の高校からの友人で、左腕が肘までしかない。さばさばとした人物だが、高校時代はクラス委員で面倒見がよく、周囲の人の変化にもよく気付く。桂が飼い猫を亡くして沈んでいたときには真っ先に気付いて声をかけ、それがきっかけで友人になった。プライドが高く、他人を頼りにしたりしない。周囲から頼られることで、そんな自分を支えている。物語を通して、彼女の内面はほとんど描かれないが、描かれないことこそが彼女を表している。桂は愛のことを尊敬しつつ、その危うさを心配しているように感じられる。
自称・隻腕の美女。桂の高校からの友人で、左腕が肘までしかない。さばさばとした人物だが、高校時代はクラス委員で面倒見がよく、周囲の人の変化にもよく気付く。桂が飼い猫を亡くして沈んでいたときには真っ先に気付いて声をかけ、それがきっかけで友人になった。プライドが高く、他人を頼りにしたりしない。周囲から頼られることで、そんな自分を支えている。物語を通して、彼女の内面はほとんど描かれないが、描かれないことこそが彼女を表している。桂は愛のことを尊敬しつつ、その危うさを心配しているように感じられる。
マイノリティとマジョリティ
日和と親交を深めた桂は、日和とその仲間が集まる場に顔を出すようになる。
世の中では、障害者はマイノリティであるということになっているが、日和の仲間は重病者や障害者が多く、その集まりでは桂がむしろマイノリティであるとも言える、というパラドックスが起こっている。
また、日常生活においても、桂自身がマイノリティ、というか、少数派であったり、疎外感を感じるシーンはいくつも描かれている。例えば地震が起こった際、阪神・淡路大震災を思い出して怯えたり、昔話に盛り上がったりする周囲の友人たちをよそに、どんな表情をしたらいいかも分からないまま、聞いていることしかできなかったり、関東から越してきたばかりの頃、土地勘のなさや言葉の違いから、故郷から遠く離れてしまったことを感じたり。マイノリティとは違うかもしれないが。ただ、マジョリティやマイノリティ、多数派、少数派などというのは絶対的なものではなく、周囲と比べてどうか、という相対的なものであるのだろうと思う。
自分がどこに属しているかではなく、一人の人間と人間として対等に付き合うとはどういうことかを、この作品では描いているように感じる。
余談
「障害」ではなく「障がい」「障碍」という表記が広がっているが、私自身はどちらでも良いのではないか、「障害」で通っているならそれで良いではないかと思っている。
大学時代、部活の後輩で、右手の指がない人がいた。彼は「僕は『障害』でいいと思ってます。だって事実、僕にとっては『障害』ですもん。生きづらいですもん」と言っていた。本人がそう言っているなら、そうなんじゃないかと思うのである。ちなみに彼は、両親から愛され、大切に育てられた一人っ子で、治療にお金をかけてもらえたことを感謝しており、でもそんな環境だったから少々わがままなところもある、普通の人である。
そもそもこの問題に限らず、大騒ぎするのは大抵、当事者ではなく周辺にいる人々であることが多いように思う。当事者は騒いでも仕方ない、というか騒ぐことが逆効果であることを知っている。
元々は良い意味だった呼称が時を経て揶揄する言葉になるように(例えば「意識高い系」とか)、言葉の是非がそれを使う人々の心情と一致しないなんてことはザラにある。表面的なものではなく、考え方を変え、世の中を変えねば、意味がないのである。
というか、呼称はともかく、「障害者」「健常者」なんてひとくくりにすることにも意味はない。